「悪夢を見る理由」
~悪夢ばかり見る~
夢を見る理由
 脳は経験したことや考えたことなどの情報を睡眠中に整理し、記憶を定着させています。 定着させた記憶はカテゴリー別に脳内に留めていて、睡眠中にその記憶を出し入れしながら記憶の情報を整理しています。この過程の中で記憶が再生されて夢がみえると考えられています。ですので、ご本人が経験したことや考えたことが夢の中で断片的にでてくるのですが、映画鑑賞や読書などの本人の体験や想像したことにも影響されてストーリーが作られます。そのため夢の内容は現実的なものから、幻想的なものまで様々です。睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠がありますが、特にレム睡眠では体は休んでいますが、脳は活発に働いていて覚醒しているときと近い状態にあり、夢を見やすくなります。
脳は経験したことや考えたことなどの情報を睡眠中に整理し、記憶を定着させています。 定着させた記憶はカテゴリー別に脳内に留めていて、睡眠中にその記憶を出し入れしながら記憶の情報を整理しています。この過程の中で記憶が再生されて夢がみえると考えられています。ですので、ご本人が経験したことや考えたことが夢の中で断片的にでてくるのですが、映画鑑賞や読書などの本人の体験や想像したことにも影響されてストーリーが作られます。そのため夢の内容は現実的なものから、幻想的なものまで様々です。睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠がありますが、特にレム睡眠では体は休んでいますが、脳は活発に働いていて覚醒しているときと近い状態にあり、夢を見やすくなります。
悪夢とは
 恐ろしい夢や怖い夢、嫌な夢や不吉な夢など、恐怖や焦りなど不快な感情を引き起こす夢を一般的に悪夢と言います。「悪夢のようなシナリオだ」というような例えでも使われることからも分かるように、悲惨なことや嫌なことを表現する言葉としても用いられます。悪夢はほとんどの方が経験することであり、異常ではないことが多いですが、悪夢を頻繁に見る場合には何かしらの病気やストレスが原因となっていることがあります。
恐ろしい夢や怖い夢、嫌な夢や不吉な夢など、恐怖や焦りなど不快な感情を引き起こす夢を一般的に悪夢と言います。「悪夢のようなシナリオだ」というような例えでも使われることからも分かるように、悲惨なことや嫌なことを表現する言葉としても用いられます。悪夢はほとんどの方が経験することであり、異常ではないことが多いですが、悪夢を頻繁に見る場合には何かしらの病気やストレスが原因となっていることがあります。
悪夢の原因
精神的要因、素質
ストレスをため込みやすい性格や、不安や恐怖を感じやすい性格は、夢の中でも不安や恐怖が表れやすくなります。日常生活におけるストレスや不安が悪夢を誘発する要因となります。仕事や家庭でのプレッシャー、重要な決断を迫られる状況などが悪夢の背景にあることがあります。
環境要因や生活習慣
睡眠の質が低下すると夢をみる頻度が高まります。騒音や光が入る寝室、不適切な室温や湿度での睡眠環境は、睡眠の質を低下させてしまい悪夢を見る頻度を増やすことがあります。また不規則な就寝時間や交代勤務などの生活リズムの乱れから、体内時計が乱れて、睡眠と覚醒のリズム障害が生じると睡眠の質を低下させます。これにより、不快な夢を体験する可能性が高まります。
悪夢障害
本人の生命や安全を脅かすとても恐ろしい内容の夢をみます。覚醒時には夢の内容を生々しく覚えており、時に同じ内容の悪夢を繰り返し見ることがあります。恐怖のあまり睡眠の途中で飛び起きてしまい、その後、再入眠できないこともしばしばあります。同時に交感神経が活性化して心臓がドキドキしたり、汗をかいたりします。眠ることの恐怖から不眠になることもあります。これにより日中の活動に影響が出てしまいます。
レム睡眠行動障害
レム睡眠中は正常では筋肉が弛緩しており、夢をみても同時に体が動くことはないのですが、レム睡眠行動障害では筋緊張の低下が起こらず、夢の内容がそのまま行動として起こります。たとえば、湖の中に飛び込む夢を見ながら、ベッドの上でその行動をとってしまうなどです。この行動異常により患者様だけでなく添い寝しているパートナーが打撲などを受傷することがあります。50歳から60歳の男性に好発します。
パーソナリティ障害や統合失調症
ある種のパーソナリティ障害(統合失調症型パーソナリティ障害、シゾイドパーソナリティ型、境界性パーソナリティー障害)や統合失調症では自我の境界が薄れたり曖昧になったりすることで悪夢を見やすい傾向があると言われています。
不安障害
不安障害にはいくつかの分類がありますが、なかでも全般性不安障害では、日常生活の様々なことに対して強い不安が起こり恐怖心として自覚されます。これにより生活に影響を及ぼします。過度な不安や恐怖が夢の中でも再現されやすく、日ごろから心配している事柄についての恐怖体験をすることがあります。
うつ病
うつ病は憂うつな気分とともに自尊心が低下し、無価値感にさいなまされます。また、不眠が起こり、レム睡眠の時間が長くなります。これにより夢を見やすい状況になります。自己のイメージは否定的なものになり、自殺念慮が出てくる方もいます。ネガティブな思考が強くなり、死について考える機会が増えると夢の中でも、不快な夢を見ることがあります。
心的外傷後ストレス障害(PTSD)、トラウマ体験
心的外傷後ストレス障害(PTSD)は自然災害、酷い事故、性的暴行、変死体の目撃などの多くは日常では滅多に経験することのないような強い心的外傷(トラウマ)によって引き起こされます。 症状のひとつにフラッシュバックと呼ばれる再体験症状があり、夢の中でトラウマを再体験する悪夢が含まれます。PTSDの悪夢は実際の出来事の回想であることが多いです。
薬物による影響
レム睡眠を増加させるスボレキサント(ベルソムラ)など一部の睡眠薬の副作用で悪夢を見ることがあります。非ベンゾジアゼピン系薬剤の急速な中止により、それまで抑制していたレム睡眠を増加させ悪夢を見ることがあります。パーキンソン病治療薬のL-ドパ、頻脈や高血圧治療薬のβブロッカーなどの副作用で起こることもあります。 その他、アルコールや覚せい剤の乱用でも悪夢が起こります。
悪夢の対処法
ご自身でできる悪夢の対処法は、寝室の環境調整、生活習慣の改善、恐怖体験を避ける、就寝前のリラックス、悪夢の内容をコントロールするなどがあります。
- 寝室に入ってくる光や騒音を避けて、室温や湿度の管理をすることで睡眠環境を整えましょう。
- 睡眠と覚醒のリズムを整えるために、同じ時間に起床し、同じ時間に就寝できるよう生活習慣を改善しましょう。
- ホラー映画やサスペンス小説などの不安や恐怖体験を感じる媒体を控えるようにしましょう。
- 就寝前に温めのお湯に長く入浴したり、アロマをたいたり、ヒーリングミュージックを聞いたりしてリラックスしましょう。
- 悪夢のストーリーを書き出して、その結末をご本人にとって良いものに書き換えてみましょう。例えば、「獣に追いかけられる悪夢を、実は魔女の呪いで獣の姿にされた王子様で、追われた後に恋に落ちた」などイメージリハーサル法と呼ばれる手法があります。
悪夢で受診するタイミングは?
不吉な夢や嫌な夢はほとんどの方が経験することであり、異常ではないことが多いですが、悪夢を頻繁に見る場合には何かしらの病気やストレスが原因となっていることがあります。 受診を考えるタイミングとしては次のような場合で、睡眠自体に影響が出てしまい日中の活動に支障をきたしたり、気分や感情に変化が出てきたときです。
- 悪夢を毎晩のように見る
- 悪夢で目覚めてしまい再入眠できなくなった
- 眠ることへの恐怖が強くなり入眠できなくなった
- 悪夢により疲労がとれず日中の倦怠感、集中力の低下がある
- 徐々に憂うつな気分になってきた
- イライラすることが増えてきた
など
悪夢 まとめ
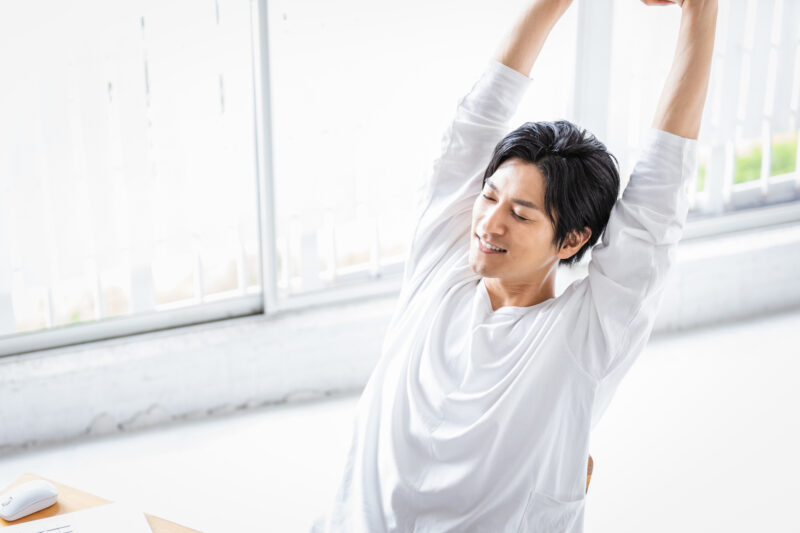 恐怖や焦りなど不快な感情を引き起こす夢を一般的に悪夢と言います。悪夢はほとんどの方が経験することであり、異常ではないことが多いですが、頻繁に悪夢を見る場合には何かしらの病気やストレスが原因となっていることがあります。特に、悪夢により不眠が続き日中の活動に影響が出たり、気分や感情に変化が出てきたときは、放っておかずに精神科・心療内科を受診することをお勧めします。
恐怖や焦りなど不快な感情を引き起こす夢を一般的に悪夢と言います。悪夢はほとんどの方が経験することであり、異常ではないことが多いですが、頻繁に悪夢を見る場合には何かしらの病気やストレスが原因となっていることがあります。特に、悪夢により不眠が続き日中の活動に影響が出たり、気分や感情に変化が出てきたときは、放っておかずに精神科・心療内科を受診することをお勧めします。

